【弁護士解説】離婚における親権者の決定|裁判所の判断基準となる重要原則と裁判例
離婚に際し、未成年のお子さんがいる場合に避けて通れないのが親権者の指定です。この問題は、当事者間の協議のみならず、法的な手続きにおいても極めて重要な論点となります。
本稿では、親権者を指定する上での法的な手続と原則、そして判断の基礎となる裁判所の考え方について、専門的な知見に基づき客観的に解説します。
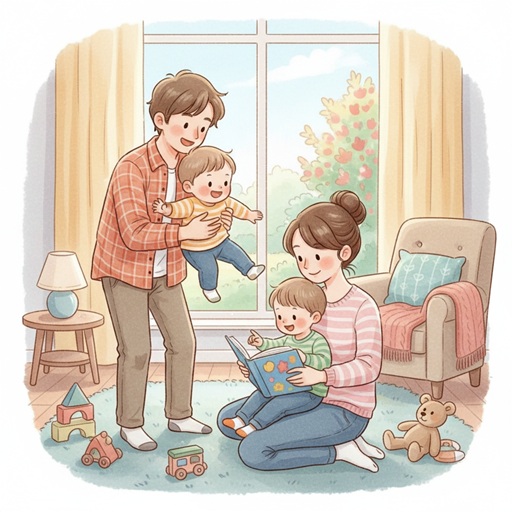
親権に関する基本事項
まず、親権に関する基本的な法律上の定義と制度について解説します。
Q. そもそも「親権」とは何か?
A. 親権とは、未成年の子が一人前の社会人として成長するために、親に認められた権利と義務の総称です。法律上、主に以下の2つの要素から構成されます。
身上監護権
子と一緒に暮らし、身の回りの世話や教育を行う権利義務です。具体的には、居所の指定、懲戒、職業の許可などが含まれます。
財産管理権
子が有する財産を管理し、子が行う法律行為を代理する権利義務です。例えば子が何らかの契約を結ぶ際に、親が代わりに結ぶことなどがあります。
法務省HPはこちら
Q. なぜ、離婚時に親権者を必ず指定する必要があるのか?
A. 日本の民法では、父母が婚姻中である間は共同で親権を行使しますが、離婚後は父母のいずれか一方を親権者として定めなければならないと規定されています(単独親権制度)。
子の福祉の観点から、進学や医療行為への同意、契約など、子の生活に関する重要な法律行為を行う主体を明確にする必要があるためです。そのため、離婚届には親権者を指定する欄が設けられており、この指定がなければ離婚届は受理されません。
親権者指定の判断枠組み
父母間の協議で親権者が定まらない場合、最終的には家庭裁判所の判断に委ねられます。裁判所は、「子の利益」を最も優先する観点から、以下の諸事情を総合的に考慮して判断します。
判断の基軸となる主要原則
監護の継続性(現状維持の原則)
子の心身の安定を図るため、これまでの監護状況を維持することが重視されます。したがって、離婚前から子を主として監護してきた親が、引き続き親権者として指定される傾向が強いです。特に子が乳幼児であるほど、この原則の重要性は高まります。
子の意思の尊重
子が一定の年齢に達している場合、その意思は判断において重要な要素となります。実務上、おおむね10歳以上で子の意思が考慮され始め、15歳以上の子については、裁判所はその陳述を聴取することが法律で義務付けられています。
総合的に考慮されるその他の事情
上記の主要原則を基に、以下の事情も総合的に評価されます。
- きょうだい不分離の原則 きょうだいは相互に影響を与えながら人格形成をすることから、可能な限り分離すべきではないとされています。
- 面会交流への許容性 離婚後、非監護親と子との間で適切な面会交流を実施することに寛容な姿勢であるかは、子の福祉の観点から考慮されます。
- 監護開始の違法性 一方的な子の連れ去りなど、違法な手段で監護を開始した場合、親権者としての適格性を欠く事情として不利に考慮されることがあります。
- 婚姻関係破綻の有責性 不貞行為等の有責性は、それ自体が直ちに親権者の適格性を否定するものではありません。しかし、その行為が子の福祉に具体的な悪影響を及ぼしていると認められる場合には、判断の一要素となります。
参考となる裁判例の解説
例:面会交流に対する姿勢の評価(東京高判平成29年1月26日判時2325号78頁)
【事案】
離婚後、年間100日の面会交流計画を提示した父と、5年以上子を監護してきた母との間で親権が争われました。
【本判例のポイント】
本決定は、「面会交流に寛容な親を優先すべき(寛容性の原則)」という考え方が、唯一絶対の基準ではないことを示唆しました。裁判所は、将来の面会交流の約束よりも、過去から現在に至るまでの安定した監護実績という事実を重視する姿勢を維持していると分析できます。
その他
平成24年から令和4年までの間に判断された主要な裁判例を横断的に研究すると、以下のことが言えます。
①監護の継続性は重要な要素で、特に「主たる監護者が父母のどちらと認定できるか」がほとんどの事案で指摘されています。例外的に、父母が同等の割合で監護している場合にはその他の考慮要素を検討することになりますが、そのような事案は極めて稀なのが現状です。
②子の成長の程度に応じて子の意思も尊重されますが、その希望が述べられるに至った経緯や監護状況も考慮すると、子の希望を重視すべきか否かは事案により異なります。例えば、子どもを一方的に奪って別居した事案では、連れ去った親の言いなりになる可能性(片親疎外)があり、そのような場合には子の希望は親に誘導されたものとして重視されない傾向があります。
③その他きょうだいがいる場合にはきょうだい不分離の原則が基本的に採用されますが、あくまでも一考慮要素に留まります。そのため、例えば父母が近い位置に住んでいてきょうだい同士の交流が頻繁に行われている場合や、きょうだい全員を引き受けると監護水準が維持できなくなるような場合には、分離を許したうえで、面会交流で調整を図るというやり方が採られることもあります。
結論
以上、親権者指定に関する法的な判断枠組みについて解説しました。実際の事案では、ここに挙げた要素が複雑に絡み合い、専門的な評価が必要となります。
個別の事情が法的にどのように評価されるかについては、具体的な事実関係に基づいた詳細な検討が不可欠です。
専門家による客観的な分析と見通しをご希望の場合は、初回無料ですので、ご相談ください。
解決事例
・子どもを残したままの別居から半年後に親権・監護権を獲得できた離婚の解決事例|宮崎県の離婚弁護士(みなみ総合法律事務所)



 宮崎県宮崎市老松1-2-2
宮崎県宮崎市老松1-2-2 宮崎県都城市上町13-18
宮崎県都城市上町13-18 宮崎県延岡市中町2丁目1-7
宮崎県延岡市中町2丁目1-7