【弁護士が解説】相続放棄で借金を回避するために知っておくべき全知識
大切なご家族が亡くなられた後、遺されたご遺族には悲しむ間もなく、相続という現実的な問題が訪れます。プラスの財産だけでなく、思わぬ借金が見つかるケースも少なくありません。
「故人の借金も相続しなければならないの?」「借金を相続しない方法はないの?」
今回は、そんな不安を解消するための重要な手続きである「相続放棄」について、その仕組みから注意点まで詳しく解説していきます。
1 相続の基本ルール:プラスの財産も借金もすべて受け継ぐ
ご親族が亡くなられた場合、その方が多額の借金を背負っていたというご相談は非常に多く寄せられます。このような場合、ご遺族である相続人は、故人の借金を支払い続けなければならないのでしょうか?
残念ながら、何もしなければ、その借金を支払わなければならなくなる可能性が極めて高いです。
なぜなら、民法という法律で「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定められているからです(民法第896条)。これは、亡くなった方(被相続人)が持っていた財産のすべてを、相続人が受け継ぐことを意味します。
「すべて」という点には、以下の両方が含まれます。
プラスの財産(積極財産):預貯金、不動産(土地・建物)、株式、自動車など
マイナスの財産(消極財産):銀行や消費者金融からの借金、住宅ローン、未払いの税金や家賃、誰かの保証人になっているという地位など
つまり、法律上、相続人はプラスの財産だけを選んで相続することはできず、原則として借金などのマイナスの財産もセットで引き継ぐことになるのです。

2 借金を回避する手段「相続放棄」とは?
では、相続人はどのような場合でも諦めて、故人の借金を支払うしかないのでしょうか。
ご安心ください。そのような事態を避けるために、法は「相続放棄」という制度を設けています。このルールを活用することで、借金の相続を法的に回避することができます。
相続放棄とは、その名の通り、相続に関する一切の権利と義務を放棄し、「初めから相続人ではなかった」ことにする手続きです(民法第939条)。
相続放棄のメリット
最大のメリットは、故人の借金を一切支払う必要がなくなることです。「初めから相続人ではなかった」とみなされるため、債権者から支払いを請求されても、法的に断ることが可能になります。
相続放棄の注意点・デメリット
非常に有効な制度ですが、利用する際にはいくつか重要な注意点があります。
プラスの財産も一切相続できなくなる 相続放棄は、マイナスの財産だけを放棄する制度ではありません。預貯金や不動産といったプラスの財産もすべて手放すことになります。後から価値のある財産が見つかったとしても、相続することはできなくなります。
一度手続きが完了すると、原則として撤回できない 家庭裁判所で相続放棄の手続きが正式に受理された後、「やはり財産が欲しくなった」といった理由で取り消すことは、原則として認められません。慎重な判断が必要です。
相続権が次の順位の相続人に移る 例えば、第一順位の相続人である子全員が相続放棄をすると、次に相続権は第二順位である故人の父母(または祖父母)に移ります。そして、父母もすでに亡くなっている場合や、父母も相続放棄をした場合には、第三順位である故人の兄弟姉妹へと移っていきます。借金の支払い義務が、意図せず他の親族に移ってしまう可能性があるため、相続放棄をする際は、次の順位の相続人へその旨を伝えておくことが親族間のトラブルを防ぐ上で重要です。
ご自身が「保証人」になっている債務は残る 相続放棄は、あくまで「亡くなった方の」借金の支払い義務を免れる制度です。もし、ご自身がその借金の保証人や連帯保証人になっている場合、その保証人としての支払い義務はご自身のものとして残ります。これは相続とは別の問題ですので、注意が必要です。
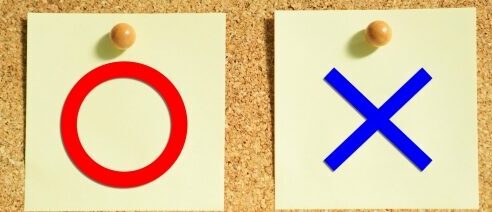
3 相続放棄の具体的な手続き
では、具体的な手続きはどのように進めるのでしょうか。
いつまでに、どこで手続きするのか?
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、「亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に申述(申立て)をして行います(民法第915条・第938条)。
この3ヶ月という期間(熟慮期間)を、特に何の手続きもせずに過ぎてしまうと、原則として相続を「単純承認」した、つまりプラスの財産もマイナスの財産もすべて無限に受け継ぐことを認めたものとみなされてしまいます(民法第921条2項・第920条)。
なお、財産調査に時間がかかり、3ヶ月以内に判断ができないといった事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで、この期間を伸長(延長)してもらえる場合があります(民法915条1項但書)。
手続きに必要な主な書類
申立てには、主に以下のような書類が必要となります。誰が放棄するか(子、配偶者、兄弟姉妹など)によって必要書類は変わります。
相続放棄の申述書
亡くなった方の住民票除票(または戸籍附票)
申述する人(放棄する人)の戸籍謄本
亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 など
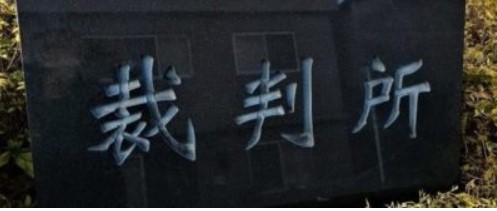
4 相続放棄ができなくなる!?注意すべき「法定単純承認」とは
3ヶ月の期間内であっても、相続人が特定の行為をすると、相続を承認したものとみなされ(法定単純承認)、相続放棄ができなくなる場合があります。特に注意が必要なのは以下のケースです(民法第921条)。
相続財産の全部または一部を処分したとき 例えば、亡くなった方の預貯金を引き出して自分のために使ったり、不動産を売却したり、ご自身の名義に変更したりする行為がこれにあたります。財産価値のある遺品を勝手に処分したり売却したりする行為も「処分」と見なされる可能性があります。
相続財産の全部または一部を隠したり、個人的に消費したりしたとき 借金から逃れるために、プラスの財産があることを意図的に隠すなどの背信的な行為があった場合も、相続放棄は認められません。
「形見分けだから大丈夫だろう」「葬儀費用に充てるだけだから」といった自己判断で故人の財産に手をつけてしまうと、後々、相続放棄が認められないという深刻な事態に繋がりかねません。判断に迷う場合は、必ず事前に専門家へご相談ください。
5 まとめ:お悩みなら、お早めに弁護士へ
故人が遺した借金の問題は、相続放棄という制度を上手く活用することで解決できる場合があります。
しかし、「3ヶ月」という厳格な時間制限があり、その間に必要書類を集め、故人の財産状況を調査し、放棄すべきかどうかを判断しなければなりません。また、一つ行動を間違えるだけで、放棄が認められなくなるリスクも伴います。
「手続きを自分で行うのが不安だ」「資料の収集が難しい」「3ヶ月の期間が迫っている」など、少しでもご不安な点があれば、お一人で悩まず、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。相続に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士が、皆様にとって最善の解決策をご提案いたします。
【宮崎事務所】宮崎市老松1-2-2 宮崎県教職員互助会館2階(宮崎駅から徒歩5分、モリタゴルフ宮崎店の隣)
【都城事務所】宮崎県都城市上町13-18 都城STビル6階(西都城駅から徒歩5分、都城合同庁舎近く)
【延岡事務所】宮崎県延岡市北町1-3-19 米田ビル2階(延岡市役所~延岡シネマの通り沿い)
※宮崎県のすべての地域に対応致します。県外の方のご相談も承っております。



 宮崎県宮崎市老松1-2-2
宮崎県宮崎市老松1-2-2 宮崎県都城市上町13-18
宮崎県都城市上町13-18 宮崎県延岡市中町2丁目1-7
宮崎県延岡市中町2丁目1-7